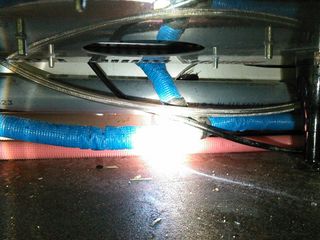ゴキブリの好きな食べ物3種類
2017-01-06 [記事URL]
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は格別なお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
2017年も張り切って、季節や時事に見合った害虫・衛生・健康の内容を配信していきたいと考えております。
今後、何か配信ご希望の内容がございましたら、随時受け付けておりますので、下記アドレスよりご返信の程お願い申し上げます。
少しずつでも、確実に、お客様満足の向上を目指し邁進してまいります。
今年も皆様に更なるご満足をお届け出来る様、精一杯努力してまいりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
早速ですが、お正月は美味しい食べ物がたくさんありましたね。
そこで、新年最初の配信は「ゴキブリの好きな食べ物3種類」についてです!
ゴキブリの好きな食べ物3種類
ゴキブリは“食品害虫”であることをご存じでしょうか。
つまり、ゴキブリの好きな食べ物を、テーブルの上やキッチンなどに放置しておくと、ウジャウジャ増殖する可能性があります。
もし食べ物を放置していたら、ゴキブリがそれを食べ、私たち人間が気づかずにまたその食べ物を食べたり、調理に使用していたりする可能性があります。
想像するだけでも恐ろしいです。
そこで、ゴキブリ撃退の予備知識として、ゴキブリの好きな食べ物3種類をご紹介します!
■1:小麦粉、茶の葉など“植物性乾燥食品”
ゴキブリが好きな食べ物の1種類目は、“植物性乾燥食品”です。
(具体的には、小麦粉やパン粉、茶の葉、乾物など。)
こういった食品は、開封後の保管に一定の注意を払っておくことをお勧めします。
例えば、“小麦粉”は開封をしたら、低温・低湿度の場所で密封容器に入れて保管するようにしましょう。
袋のままだったり、容器のふたが半開きだったりすると、ゴキブリを寄せ付けてしまいます。
■2:パン・惣菜など“調理・加工食品”
2種類目の好物は、パンや惣菜、お菓子などの“調理・加工食品”です。
食べかけのものをテーブルに放置していないでしょうか。また、惣菜のパックを洗おうと流し台に置いたまま翌朝を迎えていた、なんてことはないでしょうか。
放置していた食べかけのものを再度食べるのは絶対に止め、容器を捨てる際には、すぐに水洗いしてからゴミ箱に捨てるようにするのが確実です。
くわえて盲点となりやすいのが、“ペットのエサ”です。
ゴキブリから見たら、ドッグフードもエサとなりますので、大量発生の原因の1つと言えます。
必ず食べ残しは処分するようにしましょう。
■3:肉や魚類
精肉やソーセージ、魚など“肉や魚類”も、ゴキブリの好物です。
気をつけたいのが、調理をしている時にコンロの周辺に飛ぶケースや、食べカスが排水溝に残っているケースなどです。
人間から見たらほんのわずかだったとしても、ゴキブリからしてみたら、大きなエサです。
今は寒さが厳しい冬ですので、比較的ゴキブリの発生は落ち着いていますが、ゴキブリの最盛期である夏は特に、調理後はこまめに食べカス等を取り除くように心掛けましょう。
―いかがでしたでしょうか。
「これくらいなら大丈夫」の油断が、ゴキブリを大量発生させてしまいます。
食べ物の取り扱いに注意を払い、ゴキブリ撃退の環境作りをして頂ければ幸いです。

 バーカウンターに粘着マットを引き終わった瞬間に4匹捕獲です。
その後、厨房と客席を粘着マットを引きましたが捕獲がなく退店しました。
バーカウンターに粘着マットを引き終わった瞬間に4匹捕獲です。
その後、厨房と客席を粘着マットを引きましたが捕獲がなく退店しました。

 数時間後に再度入店しました。
早々にネズミの4匹の捕獲があったのであまり期待が出来ないと思いましたが・・・・・
数時間後に再度入店しました。
早々にネズミの4匹の捕獲があったのであまり期待が出来ないと思いましたが・・・・・

 ネズミ粘着マットが散らかっているではありませんか!
眺めてビックリ、ネズミが倍以上に増えていました。
捕獲が出来たのは喜びましたが・・・
予想以上の生息でしたので驚きが隠せませんでした。
次回も気合を入れて作業へ当たります。
ネズミ粘着マットが散らかっているではありませんか!
眺めてビックリ、ネズミが倍以上に増えていました。
捕獲が出来たのは喜びましたが・・・
予想以上の生息でしたので驚きが隠せませんでした。
次回も気合を入れて作業へ当たります。