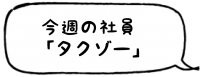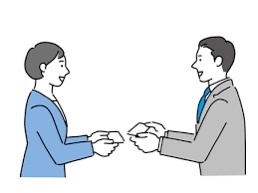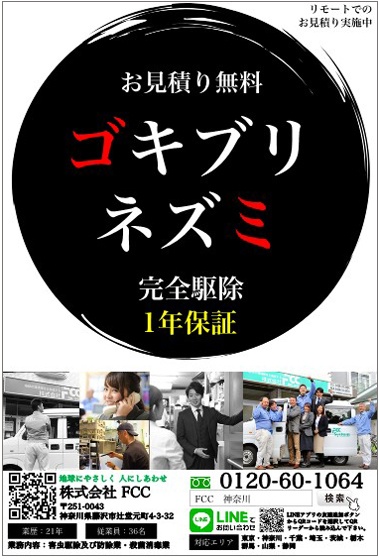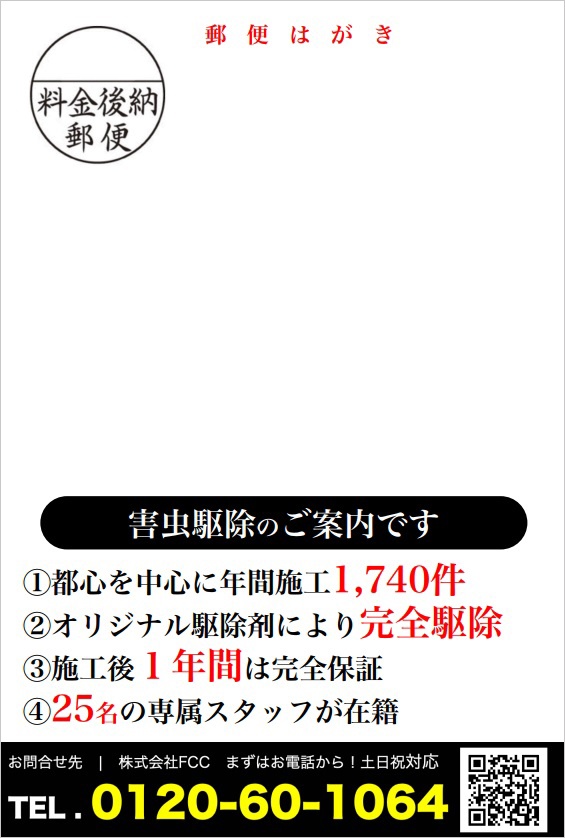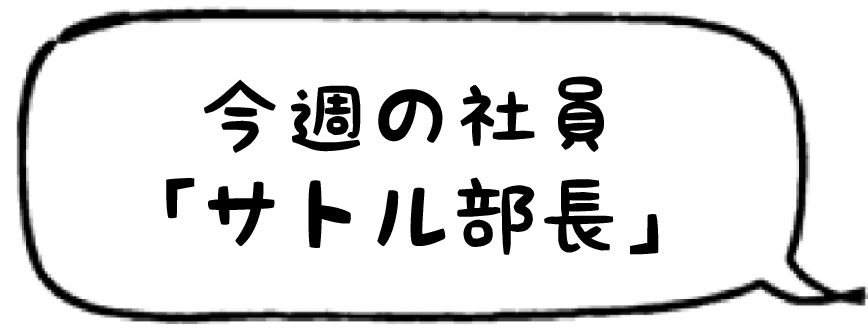新入生
2022-04-28 [記事URL]
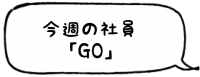

4月は新入生、新社会人が多く誕生します。
FCCにも新卒の総務スタッフが入社しました。
ゆっくり会社と業務に馴染んで、活躍してもらいたいと思います。
さて、そんな新年度の世の中ですが、この前出勤していた時の出来事です。
会社に向かい歩いていると、おばあさんに声をかけられました。
おばあ「おはようございます」
私「おはようございます」
おばあ「あなた中学生?」
私「いえ、社会人です。」
おばあ「あぁ桜井さんところの」
私「いや、桜井ではないです」
どうやら最初は中学生と間違えられたようです。
そんな私も四捨五入すると40歳。
流石に中学生は若すぎましたが、清々しい気持ちになりました。