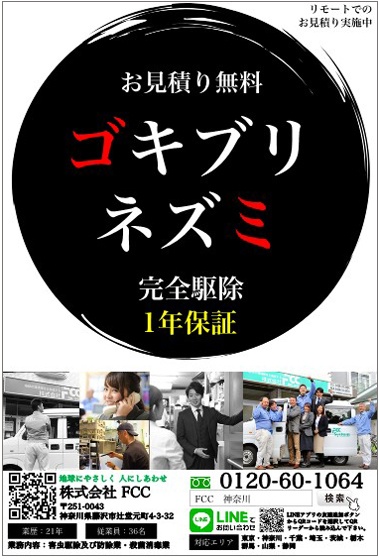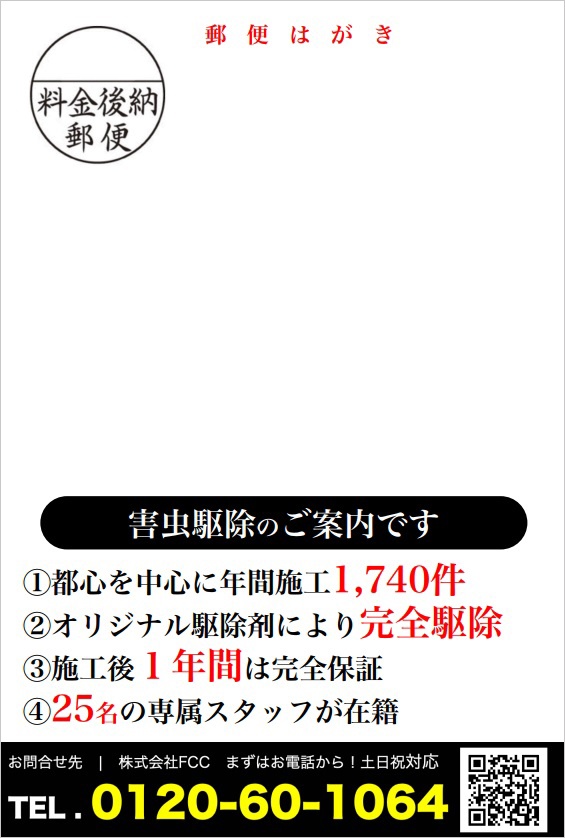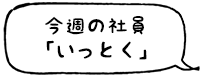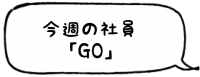梅雨の時期こそ体調管理を
2022-06-24 [記事URL]
皆様こんにちは!
6 月といえば梅雨のシーズンですよね。
梅雨の時期には、色々な体調不良に悩まされることはありませんか?
風邪・頭痛・めまい・倦怠感・体の冷え・肩こりなどなど。
実は梅雨の時期は体調を崩しやすい気候になっています。
■起こりやすい症状
1・自律神経の乱れ
気温や湿度のばらつきによって自律神経の乱れが引き起こされ
「体がだるい」「頭が痛い」などの症状が現れます。
また、一日の気温差により「冷え」「肩こり」の症状が出ることもあります。
2・湿気による不調
湿度が高くなり体内の水分が出て行きにくくなり、体のむくみの原因になります。
湿気によって食べ物が劣化するスピードも速くなるため、
カビや細菌が繁殖して「食中毒」の危険性も高まってきます。
■解消方法
・食事
ビタミンを多く含む食品や体を温める食品を取りましょう。
・睡眠
布団を湿った状態にしないなど快適に眠れる睡眠環境を整えましょう。
・運動
体の中に余分な水分がたまりやすいため、適切な運動を行うことが大切です。
運動は簡単なものでよいです。
■雨の意外な効果
・ヒーリング効果
雨音は集中力UPと空気中のマイナスイオンでリラックス効果を得ることが出来ます。
・視覚効果作用
雨の日には照度が減り、目に入る光が優しく晴天時よりも色が格段に綺麗に見えます。
・お肌絶好調
お肌にとって最適な湿度60~65%を確保出来ます。1年で最もお肌にやさしい季節です。
いかがでしたでしょうか?
梅雨はカラダの負担になることが多い時期ではありますが、
雨による素敵な効果や、アジサイや初夏に向けて美しさを増す木々たちに
小雨も加わり、趣のある季節でもあります。
自分なりの対策を取り入れて、雨にも負けず梅雨を楽しむ毎日を送ってください!