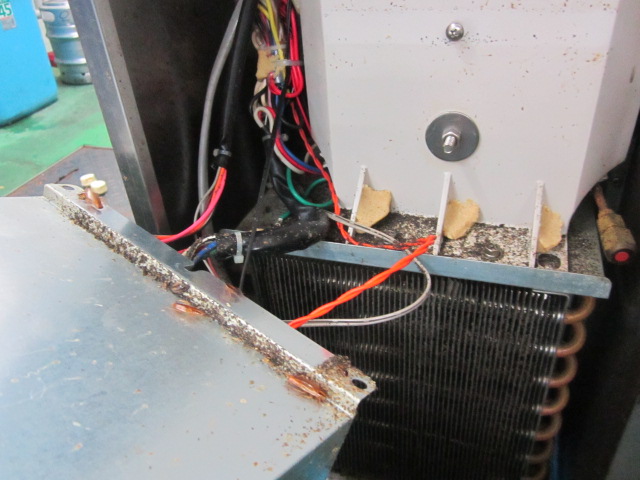乾燥と静電気
2012-02-17 [記事URL]
▼詳細
春の陽気も強まりポカポカした日も多くなってきましたが、まだまだ寒さも残っ
ています。
この時期は乾燥の為、静電気がとても起こりやすくなります。
ドアや車など触った時にバチッ!となったり、セーターやカーディガンを脱いだ際
にバチバチッ!!となった経験はみなさんもあると思います。
静電気は物体(誘導体)に摩擦などにより電荷が蓄えられ(摩擦帯電)、金属など
に触れると帯電した電気が体を通り抜ける為、バチッ!となります。
一般的には静電気というと身近で起きる現象と捉えられていますが、摩擦帯電に
よる静電気の放電はカミナリも同じ原理で、他にも産業分野(レーザープリンタ等)
で利用されています。
空気が湿っていると静電気は逃げやすいのですが、冬場は乾燥して空気中に水分
が少ないのと帯電しやすい化学繊維を用いた衣服をよく着る時期というのが重なり、
より静電気が起こりやすくなるのです。
また乾燥肌の方はさらに発生しやすいです。
対策としては空気中にしっかりと湿気を保つ事です。
最近は種類も充実している加湿機などを活用して場所に合わせてしっかり湿度を
保持していきましょう。
湿度の目安としては最低でも50%以上を保持すると帯電しにくい状態になります。
乾燥肌も気になる方は60~65%の湿度が理想的です。また、あまり湿度が高いと
今度はカビの原因になりますのでご注意下さい。
化学繊維の衣服も洗い上がりがあまりゴワゴワしない様に柔軟剤を使用すると摩擦に
よる帯電量も抑えられます。
しっかりと対策をたてて、気持ちよく春を迎えましょう。