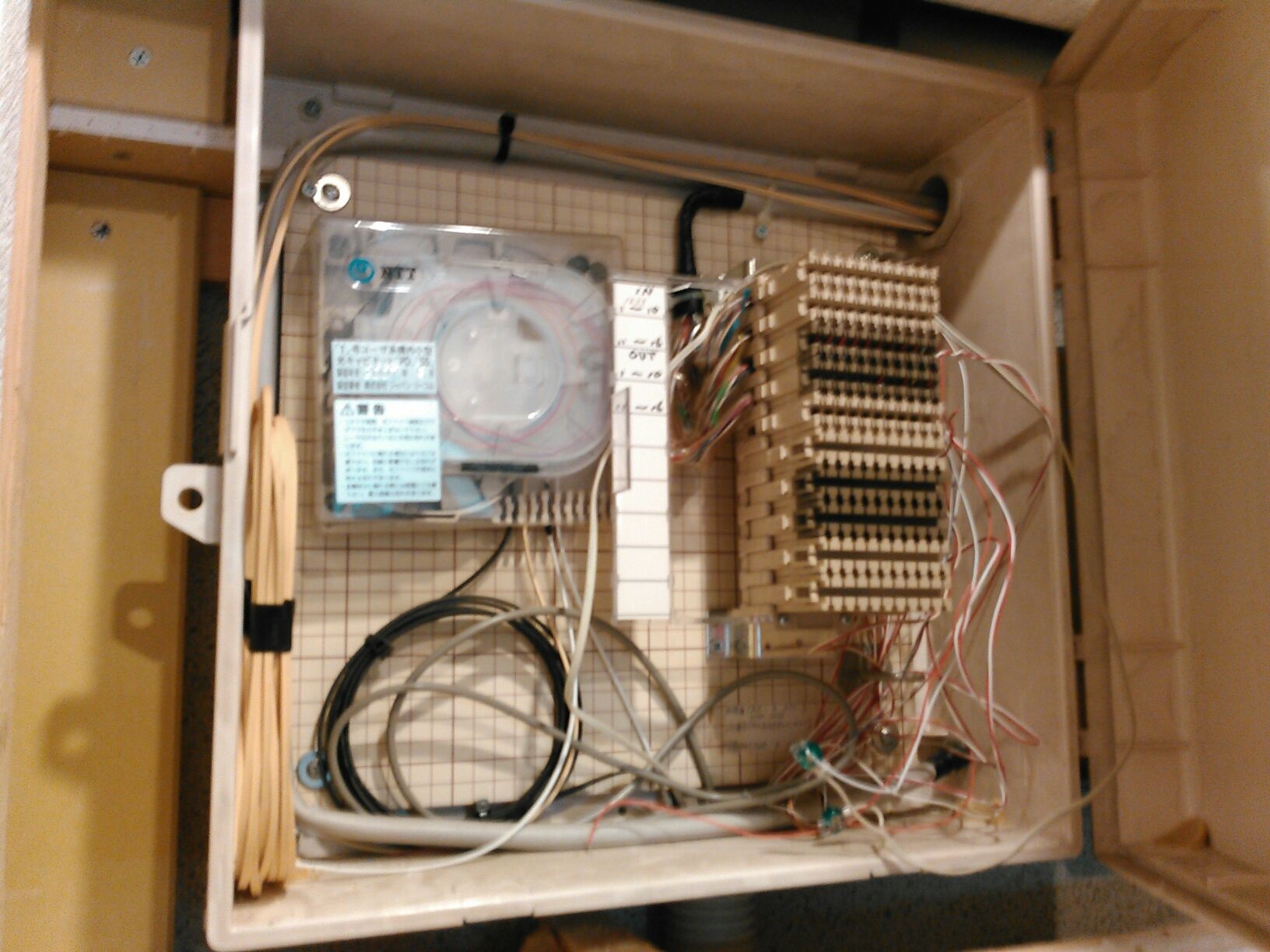都内にも感染者!はしかの予防方法公開!
2018-05-31 [記事URL]
今、巷で大流行している話題のアレといえば・・・
・・・そう。「はしか」です。
沖縄からはじまり、とうとう都内にまで感染者が出ています。
はしかは、ウィルス感染から症状が現れます。
ウィルス感染については、飲食店の方はとくに気になる話題なのではないでしょうか。
そこで今週は、はしかの予防方法についてご紹介致します。
■はしか(麻しん)とは?
空気感染、飛沫感染、接触感染により“麻しんウィルス”が感染し、症状が現れます。
感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症します。
しかし、一度感染&発症すれば、一生免疫が持続されるので、
そこはインフルエンザウィルスなどのウィルスとは違う面です。
■はしか(麻しん)を予防するには?!
マスクをし、充分に手洗いをすれば大丈夫・・・
と言いたいところですが、
それでは予防できないのが現実です。
はしかの唯一の予防方法は、
「ワクチン接種によって麻疹に対する免疫つけておくこと」です。
もちろん、日頃の手洗いうがい、風邪をひいている時はマスク着用、バランスよく栄養をとる、睡眠をよくとる、ということは非常に大切です。
しかし、はしかはこれだけでは通用しない強者なのです。
近年では、MRワクチン(麻しん風しん混合ワクチン)を「1歳の誕生日すぐ(場合によっては1歳前でも可)」と「小学校入学の前年」の二回ワクチンを接種する時代の流れになっていますが、
28歳~41歳の方は、一回しかワクチンを接種する機会がありませんでした。
中には一回もワクチンを接種したことがない方もいるので、特に注意が必要な世代になります。
42歳以上の方の場合、時代の流れ的に予防接種を受けていませんが、過去にはしかに感染&発症したことのある方が多いため、「多くの人が抗体を持っている」という認識になります。
しかし、中には42歳以上の方でも、はしかにかかったことのない方もいらっしゃるので注意が必要です。
この流行を機会に、今一度ご自身の予防接種の有無確認をしてはしかの流行に準備をして頂ければ幸いです。