秋風邪の予防と、喘息に注意
2018-09-21 [記事URL]
9月も半ばを過ぎましたね。
ゲリラ豪雨があったりとお天気が安定しませんが、いかがおすごしでしょうか。
今年の夏は大幅に気温の高い日が続きました。なので、例年よりも夏の疲れが溜まっていると感じる方も少なくないのではないでしょうか。
これから秋が深まり、冬の訪れを迎えるにつれて空気の乾燥も進んでいきます。
今回は体調面でのケアについてご紹介いたします。
■秋特有の気候
秋の季節には、移動性高気圧と移動性低気圧が上空を通過します。そのため気温や気圧の変化が大きくなります。
さらにこの季節には台風が多く日本列島を通過するため、より急激な気候変動が発生することになります。
■秋風邪の予防
気候変動とともに、空気の乾燥が進んでいきます。
乾燥により喉の痛みを感じる機会が増えるかもしれません。
冬の病気というと風邪が代表的なものですが、実は風邪の大きな原因は、冬の寒さではなく“乾燥”によるものです。
喉の粘膜が乾燥により損傷するため風邪にかかりやすくなります。
今年の様に夏の暑さで疲労の溜まりやすい状況にあると、そのリスクは増えてしまいます。
疲労の回復と風邪の予防に一番効果があるものは“十分な休養”と“睡眠”です。
睡眠時には発汗にも十分注意しましょう。
汗をかいたまま過ごしてしまうと、体を冷やしてしまいます。
肌着は吸湿性の良い天然素材の綿を着用し、枕元には水分を用意しておきましょう。
■秋は喘息にも注意
秋特有の気温気圧の変動は、気管支の収縮を引き起こし喘息の発作の原因となります。
喘息は春と秋の季節の変わり目に、悪化しやすいそうです。
喘息の原因は様々あると言われており、過労、ストレス、タバコの煙や殺虫剤等も症状悪化の引き金になるとのことです。
体調の異変を感じたら、病院で診察をうけましょう。
症状が出ていない場合でも、事前に医療機関で検査する事で、発症を防ぐ事ができます。
―いかがでしたでしょうか。
病気を引き起こす感染症の多くは、細菌やウイルスが手に付着し手を介して鼻・口・目から体内に入ることによって引き起こされるといいます。
こまめな手洗いも毎日の習慣として心掛けていきましょう。


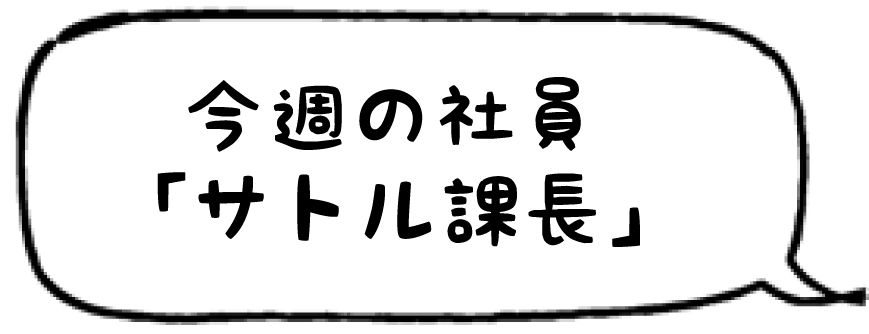



 ここ最近特にご相談の多いのがトコジラミ(南京虫)です。
まだまだ認知度はゴキブリなどに比べれば低い害虫ですが、被害は精神的、肉体的にもたらす最悪の害虫です。
今一度、このトコジラミを認識して頂き、万が一発生した場合はすぐに専門業者に依頼する事をお勧めします。
ここ最近特にご相談の多いのがトコジラミ(南京虫)です。
まだまだ認知度はゴキブリなどに比べれば低い害虫ですが、被害は精神的、肉体的にもたらす最悪の害虫です。
今一度、このトコジラミを認識して頂き、万が一発生した場合はすぐに専門業者に依頼する事をお勧めします。
 トコジラミは成虫で5~7ミリ程と目視で確認してとれます。
姿、形はカメムシによく似ています。
体の色は赤褐色で、吸血すると濃い茶色や黒っぽく見えます。血液が透けて見える為です。
症状はとにかく痒く、アレルギー反応も起こす程の激しさです。
刺し口は二つや一つとバラバラですが、1週間程は刺跡が消えないので、湿疹や蕁麻疹などのひどい状態になります。
現状では市販の殺虫剤では抵抗性がついており、駆除を完全に行う事は不可能です。
また、常に産卵して数を増やしていくため自然にいなくなる事はありません。
放っておくともうその場所では生活が出来なくなるかもしれませんので、ひどい虫刺されや、知らない発疹はトコジラミを疑って確認するようにお願いします。
トコジラミは成虫で5~7ミリ程と目視で確認してとれます。
姿、形はカメムシによく似ています。
体の色は赤褐色で、吸血すると濃い茶色や黒っぽく見えます。血液が透けて見える為です。
症状はとにかく痒く、アレルギー反応も起こす程の激しさです。
刺し口は二つや一つとバラバラですが、1週間程は刺跡が消えないので、湿疹や蕁麻疹などのひどい状態になります。
現状では市販の殺虫剤では抵抗性がついており、駆除を完全に行う事は不可能です。
また、常に産卵して数を増やしていくため自然にいなくなる事はありません。
放っておくともうその場所では生活が出来なくなるかもしれませんので、ひどい虫刺されや、知らない発疹はトコジラミを疑って確認するようにお願いします。 

 今年は何だか台風か猛威を振るっていますね。
先日の台風の際には丁度休日に出勤した分のお休みを頂いておりました。
夕方から影響が強くなるとの事でしたので、早めに個人的な予定を済ませようと駅へ。
駅で何と…、もう何年も連絡を取っていなかった友達と邂逅。
いつもなら予定は大概午後からにするので、台風がもたらした再開。
何があるか分からないものだと思った休日の一時でした。
今年は何だか台風か猛威を振るっていますね。
先日の台風の際には丁度休日に出勤した分のお休みを頂いておりました。
夕方から影響が強くなるとの事でしたので、早めに個人的な予定を済ませようと駅へ。
駅で何と…、もう何年も連絡を取っていなかった友達と邂逅。
いつもなら予定は大概午後からにするので、台風がもたらした再開。
何があるか分からないものだと思った休日の一時でした。